母の死から学んだ 才は徳の子、徳は才の師 融通無碍
平成23年7月22日(金)の21時過ぎ、母が亡くなった。享年67歳、満66歳だった。
母は現在でいえばまだ若いうちだが、突如として天に召されるように帰っていった。
母の死から学び取ったこと、それは『才は徳の子であり、徳は才の師である』ということである。
この言葉は安岡正篤先生の本に記述されていたような記憶があるが、母の死で心の芯から身につまされる想いであった。
頑迷で思い上がりが強い自分を改めて痛感し、足りなさばかりが胸中を去来した。
感謝、融通無碍な心を養って、本当に大切な精神を磨かないと、父母に申し訳ないよなぁと思う。今後何かあるたびに観返したいと考え、敢えてブログに残そうと思ったのだが、結局大晦日にアップする羽目になってしまった。
母の死の経過
22歳で自分を産んだので、同級生たちからみても、若いほうだった。
病気療養のため、入院はしていたものの、まさか逝去するとはゆめゆめ思ってもいなかったので、驚きが襲った。
息を引き取る3時間前くらいまで、孫娘がお見舞いに行っており、苦しそうだったが、亡くなるような感じでは無かったということだった。
それからわずか3時間で、天に戻っていったようである。
直接の死因は呼吸困難を伴う肺不全のようだったが、肝機能が著しく低下しており、肝臓が処理しきれない水分が肺に溜まっていった。
亡くなる1時間くらい前に、妹から電話が入り、「母の容態が急変し、ひょっとしてやばいかも知れない」というものであり、当時自分は茨城県石岡市の事務所で仕事をしていたが、仕事を収めてとりあえず、いわきの実家に戻ろうと帰り支度を急いでいる中で、今度は弟から電話が入った。
「ご臨終だよ・・」
なんともあっけない最期だったが、弟と妹が死に水を取ってくれたのが救いだった。
2011年2月入院から 3.11大震災での強制退院
昨年から若干体調は悪そうだったが、今年(2011年)に入って2月の頭に、家の段差でこけてしまったことがあった。
その際に背中を打ちつけ、どうにも痛みが引かずに病院に行くと、打撲もあるけど肝機能に著しい低下が見られるということで、即入院となった。
しばらく入院生活を続け、快方に向かいつつあったが、そこであの 3.11 大震災が起こり、その際に病院の入院棟7階から1階まで歩いて非難した。
おそらく、ずっと寝たきりだった人間が、いきなり7階もの階段を歩いて降りるというのは、言語に尽くしがたい苦痛だったのだろうと想像する。
それで、病院のほうも震災後の受け入れ対応等で、てんやわんやとなり、3.13に強制退院の運びとなった。
そして、いわきが物資等の流通に大きな不安があったのと、当時は実家におふくろ一人が生活していた実情もあり、不安が重なる中で、自分が住む茨城県石岡市に呼んだのだった。
25年ぶりの母との生活
おふくろと生活するのは、自分が高校を卒業して以来だったので、25年ぶりくらいだった。
自分が実家に寝泊りすることはあったが、1日から数日程度のもので、ずっと同じ屋根で生活することは本当に久々だった。
しかも自分は高校球児で朝早く練習に出かけ、夜遅く部活から帰宅していたので、中学生時代まで遡らないと、おふくろと生活していた感覚が思い出せなかったのだ。
結果として、この2ヶ月弱の同居生活が最後の良き思い出となった。
2階に寝泊りしてもらっていたが、最初は2階に上がるのもつらそうで、なんでこんなに弱ってしまったんだと感じていたが、息子や娘が春休みであったこともあり、よく面倒を見てくれた。
おふくろも、孫と生活ができて、良い思い出となったのではなかろうか。
5月にいわきの実家へ戻る
5月の連休前に、そろそろ自分一人でも生活できそうだから、いわきの実家に戻りたいと話があった。
弟・妹は反対したが、おふくろの決意が固そうであり、5月のゴールデンウィーク初期に、実家に連れ帰った。
1月経過して再入院となることは、当時予測すらしていなかった。
戻ってすぐに、妹夫婦が実家に手すりを取り付けたりして、老人が生活しやすい環境を懸命にこさえてくれたので、安心・安堵は大きかった。
しかしおそらく実家に帰って、しばらく人が生活していなかったのと、震災によるダメージで、いろんなところが気になったのだろう。
どうにも細々とした掃除やら何やらを通常の感覚で行っていたら、やはり体調を崩してしまった。
再度の入院生活へ
体調不良は肝機能低下によるものだが、再入院となったのが6.17だった。
しばらく入院生活を続け、体調は一進一退を続けながら、それでも快方に向かうと我々は信じていた。
だが、なかなか思うように快復していかない状況だった。
結果としての遺言
息を引き取る直前の7.19(火)に、自分もいわきで仕事があり、仕事を追えた後に病院に見舞いに行くと、しばらくして弟が来たのだった。
そこで男の兄弟が揃ったところで、遺言のようなものを言い始めたのだった。
「自分はいわきに居たい。自分が死に向かっていったら決して延命措置は取るな。そして死後、家については誰も住まないようなら解体せよ」というものだった。
帰り足で弟と、「あれは遺言のような鬼気迫る感じだったな」と互いが感じていたことを確認した。
しかし、それはもっと先のことだろうと感じていた。
その3日後に息を引き取ったのである。
使命を終えたのだろうか
父が亡くなって3年を過ぎている。おやじは最期は寝たきりになっており闘病生活が長かった。
その看病におふくろはずっと付いていた。まさにそれが仕事であるような感じで看病していた。
その疲れが出たのかとも思う。
しかし違うだろうなとも感じるのだ。おやじを見送ったことは、すなわち命であり、命に使え、自らの寿命もすり減らしていたのだろう。
逆に、おやじの死後は自分の使命を見失っていたのかも知れないなとも思う。
天晴れな最期
常々、「自分は年を取って、子どものあんたたちに迷惑をかけたくないんだよ。」と語っており、誰に迷惑をかけるでもなく、延命措置を検討する暇すらもなく、駆け足で天に舞い戻ってしまった。
ともかく我が母親ながら、天晴れな最期であった。
母に言われ続けたこと
母に言われ続けたことがある。
- 「心を穏やかにしなさい」
- 「人に対してあまり乱暴な言葉を言ってはいけない」
- 「短気を注意しなさい」
- 「今のお前はお前でちょうどよい」
- 「先祖供養をしっかりしなさい」
などであり、いまさらながらに自分の至らなさを痛感してしまう。
思えば子どもの頃、おふくろは厳しく、負けん気の固まりのようなところがあった。
同級生にケンカで負けることは無かったが、上級生に負けて家に帰ると、『勝つまでやってきなさい! それまでは家に入れることはできない!』 などという幼少時代だったのである。
晩年は、あんたがそこまで激しい気性となってしまったのは、自分の育て方に問題があったのかねぇとこぼす始末だったが・・
母はけっこう弁が立ち、自分はどれだけ話を重ねてきたか分からないくらいだ。
「命の華を咲かせる」ということを、いつも言われていたような気がする。
人は死に向かって1日1日、一歩一歩進んでいる
おふくろが死んで、当たり前だが痛感していることがある。
それは、「人は死に向かって1日1日、一歩一歩進んでいるんだなあ」ということ。
だからこそ、一瞬一瞬を大切にして、命の華を咲かせていかなければいけないなということ。
母親の死は、なんか夏場に大汗をかくように、目から汗が出てくる感覚だった。
おやじの時も葬儀は陣頭指揮を執ったが、今回も喪主を務める中、次のような言葉でご挨拶をさせていただいた。
「自分たち兄弟は、母の子どもであって本当に良かった。叶うのであれば、来世もまた親子でまみえ、そして熱く熱く苦楽をともにしたいと思う。」
これは偽ざる心境であった。
さて、これで両親ともこの世からいなくなってっしまったが、先祖供養を粛々とさせていただく所存である。
人格完成に向けて努力しなければ
おふくろに言われ続けた次のことも、身にしっかりと刻み、来年以降も人格完成に向けて努力していきたいと決意している。
- 心を穏やかにする
- 人に対して乱暴な言葉を使わない
- 短気を注意する
- 今の自分は自分でちょうどよいと達観する
- 先祖供養をしっかりする
そして冒頭に記述した、『才は徳の子であり、徳は才の師である』という意味を良く噛みしめて、感謝、融通無碍な心を養い、本当に大切な精神を磨き続けたい。
父の一周忌の際も記述してあったが、やはり母親というのはちょっとダメージがあり、少し論調が変わるなぁと苦笑いする次第だ。
















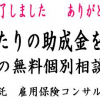
ディスカッション
コメント一覧
2年前に私の父親が亡くなった時のことを思い出しました。
私の父も闘病生活でしたが、前日の夜まで母や妻たちと会話をしていて次の日の早朝に急変し亡くなってしまいました。
連絡が来てから向かいましたが、誰も臨終には立ち会えませんでした。
亡くなった日は私の誕生日....一生忘れるなということでしょう。
大内さん
コメントありがとうございました。
そうでしたか、父上のご逝去を悼み心からご冥福申し上げます。
しかもバースデーだったとは、本当に忘れられませんね。
自分も父を4年近く前に亡くし、これで両親がこの世にはいなくなりました。
先祖供養をしっかりとさせていただかなくてはいけないと思っています。